私は公務員試験を経て、地方自治体(市役所)で公務員として約7年間働きました。
退職後は公務員試験の小論文を添削する仕事を受注した経験もあります。
ここでは、そんな元公務員が、公務員試験の小論文対策として「文章構成」について紹介していきます。
公務員になりたいと思っている人や、今後、公務員試験を控えている人はぜひ、参考にしてください。
公務員試験の小論文とは?
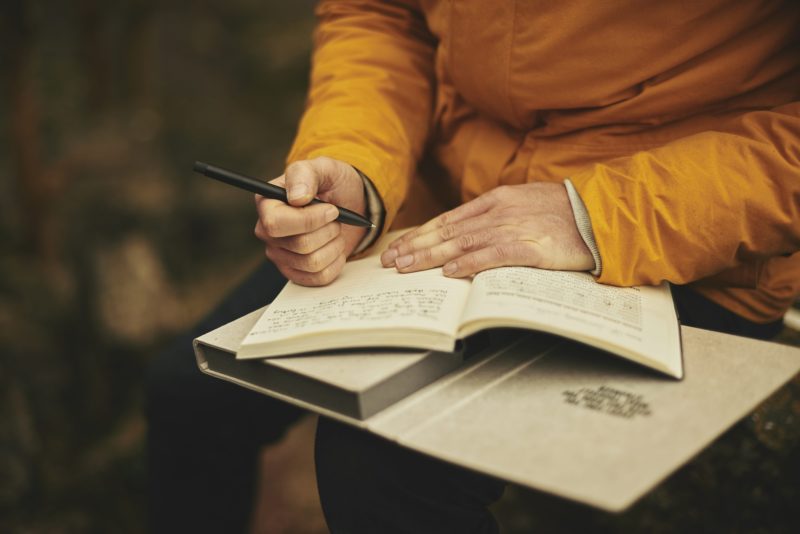
志望する自治体や公務員試験区分によって、課せられるのが小論文です。
一次試験のペーパーテストと併せて実施する場合や、二次試験以降の面接と併せて行われる場合もあります。
小論文も公務員試験を突破する上では必要な要素の一つです。
小論文を書く上で「文章構成」は文章力と同じくらい必要

小論文というだけあって、求められているのは「論じる力」です。
与えられたテーマに沿って、自分の意見を書き、最終的に結論づける小論文だからこそ、大事になってくるのが「文章構成」です。
小論文が苦手な人はまず、文章構成をマスターすることから始めましょう。
公務員試験の小論文におすすめな文章構成
では、小論文で押さえておきたい文章構成について、詳しく解説していきたいと思います。
小論文試験におすすめな文章構成は、次の三段階構成です。
①序論
②本論
③結論
今回はこの構成で小論文を書く上でのポイントを具体的に解説します。
序論のポイント

序論では、まずテーマに対する結論を述べます。
結論から文章を展開していくことで、読み手にも伝わりやすい内容になるからです。
会話でも同じことが言えるのですが、だらだらと話をされるよりも、結論から話をされた方が分かりやすいという傾向がありますよね。
小論文も同じで、まずは結論からということを念頭においてみてください。
本論のポイント

本論では、序論で述べた結論に対する理由を書きます。
「私はりんごが好きです」が序論なら、本論では「なぜ、りんごが好きなのか」を書くということ。
また、理由を一つに絞ってしまうと、最後までだらだらと文章が続いてしまったり、文字数が足りなくなってしまったりすることがあります。
本論で書く理由は一つに絞らず、2〜3つ出してみても良いでしょう。
いくつか理由を出すことで、一つの理由に対する文章がまとまりやすくなります。
結論のポイント

結論では、改めてテーマに対する回答を行い小論文を締めくくります。
改めてというのは、先に序論で結論に触れているためです。
結論で大切なのは、本論を受けたまとめの文章になるよう気をつけること。
また、序論と内容は同じになりますが、全く同じ文章にならないよう注意してください。
【実践編】公務員試験の小論文の頻出テーマで練習しよう!

では、実際にテーマを挙げて実践してみましょう。
今回選んだのは昨今、あらゆる自治体の公務員試験でも実施されている次のテーマです。
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に努めながら、経済活動を本格的に再開させていく必要があります。どのように取り組むべきか、あなたの考えを述べなさい。
まず、こちらのテーマで小論文を書いてみましょう。
書き終わった人、今すぐに書けないけど書き方が知りたいという人は、次の一例と解説で小論文の流れをチェックしてください。
【一例と解説】序論、本論、結論を意識した公務員試験の小論文
続きはnoteでも閲覧できます。




