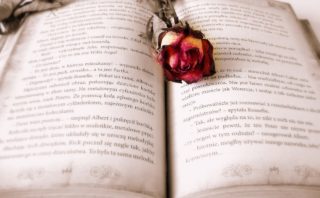公務員試験では個人面接の他に、窓口業務などのシミュレーション形式の実践が必要な自治体もあります。
バイトなどで窓口業務を経験している方であれば、そこまで気負いする必要はありません。
しかし、初めての窓口対応の場合、戸惑う方も多いのではないでしょうか。
私は7年の市役所生活のうち、入庁して3年間、窓口メインの福祉関係部署に所属していました。
本記事では、元公務員がシミュレーション形式にも活かせる窓口業務のポイントを詳しく解説します。
窓口業務の経験が無く、シミュレーション形式の試験に不安がある方はもちろん、公務員になって間もない方なども、ぜひ参考にしてみてください。
一般的な窓口業務の流れ

受付
窓口を訪ねてくる方を出迎えます。
「どうぞお掛けください」と言葉を添えて、椅子に座っていただきます。
要件確認
一般的には相手から「◯◯の手続きをしたいのですが」と要件を伝えられます。
「◯◯ですね、かしこまりました」と必要書類などを準備します。
書類確認
指定の様式に、必要事項を記入していただきます。
最終説明
書類への記入が終わると、手続きに関する説明を丁寧に行います。
不明な点が無ければ、手続きは終了です。
「お待たせ致しました。ありがとうございました」と言葉を添えて、見送ります。
窓口業務で注意すべきポイント

受付【臨機応変な対応が必要】
窓口を訪ねてくる方を出迎えます。
「どうぞお掛けください」と言葉を添えて、椅子に座っていただきます。

来庁する方によって、臨機応変な対応が必要です。
お連れ様が居る場合、人数分の椅子を用意しましょう。
車椅子の方であれば、従来の椅子を外してスペースを確保してください。
要件確認【必要な持参物が揃っていることを確認】
一般的には相手から「◯◯の手続きをしたいのですが」と要件を伝えられます。
「◯◯ですね、かしこまりました」と書類などを準備します。

手続きに必須な持参物(印鑑や本人確認書類など)がある場合、ここで確認しておきましょう。
書類へ記入していただいた後に必要書類の不足が発覚すると、時間の無駄になってしまいます。
市民の方の二度手間にならないためにも、事前の必要書類や持参物の確認はしっかりと行いましょう。
書類確認【記入ペースに合わせた説明】
指定の様式に、必要事項を記入していただきます。

ただ黙って記入している方を眺めるのではなく、項目ごとに丁寧に説明するのが理想です。
相手の記入のペースに合わせて「こちらに氏名、電話番号をお書きください」など、言葉を添えるようにしましょう。
最終説明【不明点を残したまま帰さない】
書類への記入が終わると、手続きに関する説明を丁寧に行います。
不明な点が無ければ、手続きは終了です。
「お待たせ致しました。ありがとうございました」と言葉を添えて、見送ります。

手続きによって何ができるようになったのかをきちんと伝えましょう。
また、説明後は「ご不明な点などございませんか?」と必ず尋ねるようにしてください。
窓口業務に必要な振る舞い方やポイント
笑顔

窓口は、自治体の顔です。
市役所のみならず、郵便局や銀行などでも気持ちの良い対応をしてくれる相手には誰もが好感を持つはずです。
愛想の良い職員は市民からも信頼され、次の窓口でも指名してくれる場合もあります。
ぶっきらぼうだったり、態度が悪かったりする職員は、自治体の信頼を損ねるだけでなく、そこで働く職員全員のイメージを下げてしまいます。
そのため、個人的に無愛想な職員は公務員を辞めて欲しいと思っていますし、自治体の顔でもある窓口に立って欲しくありません。
お互いに気持ちの良い窓口を行うためには、まず職員の笑顔が必要です。
まずは来庁者を出迎えるところから、笑顔で声を掛けてみてください。
配慮

とくに市民対応が多い市役所や区役所には、さまざまな方が訪れます。
デリケートな手続きや相談の場合、内容が周囲に聞こえないよう相談室に案内するケースもあります。
また、必要な持参物には個人情報も多いため、マイナンバーや電話番号などが隣の方に見えたり聞こえたりしないよう注意する必要があります。
臨機応変な対応を心掛けながら、さまざまな視点で来庁者への配慮を行いましょう。
冷静さ

怒りながら窓口にいらっしゃる方も居ます。
公務員試験のシミュレーションでも、怒った人の対応が課せられる場合があります。
怒っている方の場合、まずは相手が何に怒っていて、何を求めているのかを理解する冷静さが必要です。
「怒られた」「怒鳴られた」と思って落ち込んだり、自分を責めたりしないでください。
よっぽど理不尽な内容で無い限り、相手は何らかの目的があって窓口を訪れているはずです。
まずは話を聞いて相手を落ち着かせながら、相手に最適な手続きや案内を考えましょう。
クレーム対応に必要な振る舞い方やポイント
相手に寄り添う姿勢を見せる

まずは、寄り添う姿勢を見せることが大切です。
督促状を一斉送付した翌日、怒りながら窓口に来る方が多かったことを思い出します。
「こんな書類急に送られても困る。大体、どうしてこんな金額を払わないといけないのか?!」と怒りながら窓口に来られるのですが、まずは吐き出すだけ吐き出してもらいます。
話すうちに相手も少しずつ冷静になってくれますので、タイミングを見計らい、説明に入ります。
一方的に説明するのではなく、あくまでも対話を意識することも大切です。
出来ること・出来ないことの両方を伝える

クレーム対応では、出来ることと出来ないことの両方を明確に伝えることも大切です。
「何でこんなこともできないのか!」と責められることがありますが、官公庁は法や条例などに基づき動いているため、出来ないことは山ほどあります。
そのため、出来ないことは、何故出来ないのかを理由や根拠を添えて納得してもらえるように伝えましょう。
また、これは出来ないけれど、これは出来るというように、他の代替手段がある場合は、それを同時に提示してみてください。
クレームと意見を明確に分ける

全てをクレーム処理するのではなく、意見として受け取ることが可能な内容はきちんと処理しなければいけません。
「役所の書類が届いたから窓口に来た。難しすぎて何を書いているのか分からない。もっとわかりやすくしろ!」と言われた場合、次からはわかりやすい文章を送付できるよう努力する必要があります。
意見は拾い上げ、上司や係員と相談しながら業務改善に活かしましょう。
理不尽な内容は聞き流す

公務員になると「税金泥棒」「税金で飯を食っている癖に」という心ない言葉をかけられることもあります(実際本当にあるので驚きます)。
公務員の給料の出所は税金ですが、労働の対価として給料を貰うのは当たり前のことです。
他にも公務員だからという理由で理不尽なクレームを受けることもありますが、あまり気にしないようにしましょう。
まともに受け止めているとメンタルを壊すので、おすすめはしません。
まとめ

今回紹介したように、公務員試験にはシミュレーション形式の実践が課せられるケースもあるため、幅広く対策をおこなうことが大切です。
臨機応変な対応を心がけつつ、公務員の目線で個人情報やプライバシーに配慮しながら窓口業務をおこなってみてください。
窓口業務への不安点や、こういう場合はどうすれば良いのかといった疑問は、ぜひ質問箱をご利用ください(匿名で質問できます)。
公務員を目指している人へ、少しでも参考になれば嬉しいです。
【X(旧:Twitter)】公務員試験について知りたいことを募集中!
公務員や市役所の仕事などについて聞きたいことがありましたら、ツイッターのコメントやDMで教えてください!
匿名で質問できる質問箱も設置しているので、ご活用ください。
皆さんが求めているものを参考に、今後の記事を作っていきたいと思います。
また、ブログの記事を更新したときにはツイッターで発信しています。
ぜひ、フォローしてお待ちください。
【他の記事】元公務員が教える公務員試験におすすめの参考書・問題集
過去問や教養科目、専門科目におすすめの参考書・問題集はこちらの記事でチェックしてください。

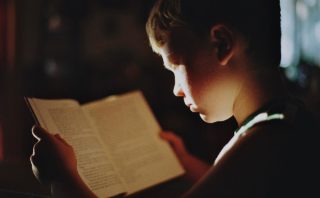


【他の記事】元公務員が教える公務員試験の小論文対策
面接に特化した記事、元公務員が教える公務員試験の小論文対策はこちらにまとめています。
未読の方はぜひ、こちらの記事も併せてお読みください。